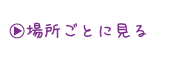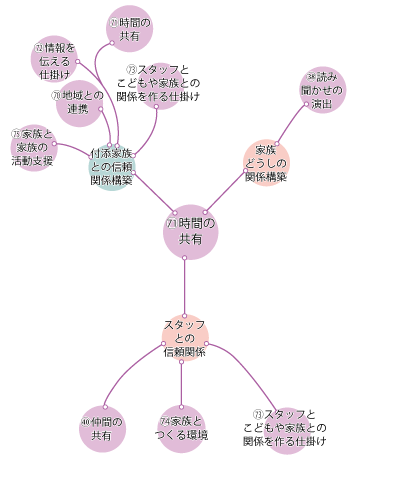
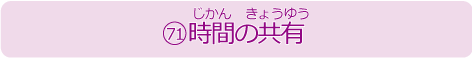
こどもは,今日という日をどのように過ごしたのでしょうか。誰と関わり、どのような体験をして、何を感じ、それがどのような発話となって現れてくるのでしょうか。
保育の時間を保育者と家庭で共有することは、こどもの体験や成長・発達を統合的に捉えることにつながります。こどもがふとした時に発する一言、それが何を意味することか、どのような背景から生じた一言かを理解して接することで、こどもの成長・発達を全面的に受け止めることができます。
またこのような情報共有は,家族での会話の端緒ともなり、その積み重ねは体験や感情を言語化することの訓練にもつながります。言語化は記憶を強化するため、望ましい行為や発話の学習効果も期待できます。
病棟など療養環境での保育場面には,家族が立ち会うことがほとんどですが,こどもたちどうしで遊んでいる様子や,保育者とこどもが検査や治療前のプレパレ−ション(58.プレパレ−ション)を行った際の反応など,共有すべきことがらはしばしばあります。
日々のちょっとしたことを書き留めておくノートやスケッチブック,小さなメモなど,話すだけではない伝達・共有の方法は,記録として残っていきます。
行事があれば,その出来事をポスター風にまとめて掲示するなどの取り組み例もしばしば見られます。一年間のイベントが,随時更新されながら展示されていれば,入院してきたこどもや家族がこれからの見通しを立てたり,期待をもって入院生活を送る手がかりにもなるでしょう。
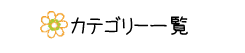
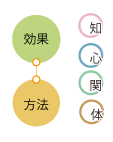

トップの写真は,保育所でのイベント報告の掲示物です。保護者がその内容を理解するとともに,こどもたちが保護者と一緒に,そのとき感じたことや自分がどのように参加したかなどを話すきっかけになっています。
保育所での取り組みの例です。その日にあったことを,保育者がスケッチブックに書いて,展示しています。時間等の関係で,1人ひとりについては書くことができなくても,「プレイルーム通信」「病棟保育通信」のようなかたちで,記録・発信していくことはできるかもしれません。
小中学生の入院などの場合には,家族が常時付添をしていない場合も多いため,このようなかたちでの記録があると,ご家族にとっては嬉しいのではないでしょうか。こうした情報提供によって保育内容を共有することで、家庭と保育者が連携してこどもの育ちを支え、またこどもの気持ちを受け止める土壌をつくっていくことができます。

これも保育施設の例ですが,この施設では,こどもたちや保護者が普段通る廊下に、日々の保育の様子を1年間の保育の流れに沿って掲示しています。保護者にとっては,こどもたちの成長の見通しとともに,1年の保育の流れの見通しもわかる仕掛けとなっています。


| 情緒の安定 | |
| 1.アプローチの期待感 | |
| 2.気持ちの切り替え空間 | |
| 3.気分転換ができる | |
| 4.小さな居場所 | |
| 5.生活やくつろぎの雰囲気 | |
| 6.治療・検査時の心的負担の軽減 | |
| 豊かな感性 | |
| 7.「触」覚のある環境 | |
| 8.遊びのなかの触覚 | |
| 9.全身で感じる遊び | |
| 10.においの体験 | |
| 11.風と気づき | |
| 12.光の体験 | |
| 13.日常的に美に触れる | |
| 豊かな心情 | |
| 14.「演じ」て理解する | |
| 15.表現する−音楽 | |
| 16.表現する−絵画,造形 | |
| 自然と生命への 畏敬と愛情 |
|
| 20.自然に親しむ | |
| 21.季節を感じ,楽しむ | |
| 22.命を感じ,親しむ | |
| 創造性の芽生え | |
| 14.「演じ」て理解する | |
| 15.表現する−音楽 | |
| 16.表現する−絵画,造形 | |
| 17.物語が編み込まれた環境 | |
| 18.遊び込める仕掛け | |
| 19.見立てを誘う環境 | |
| 豊かな言葉 | |
| 36.文字や数字がある環境 | |
| 37.知識や物語の泉に触れる | |
| 38.読み聞かせの演出 | |
| 39.ショウ&テルの機会 | |
| 思考力 | |
| 31.伝統文化を遊ぶ | |
| 32.自国の文化を知り,親しむ | |
| 33.多様性を体感する | |
| 34.電子メディアとの適切な距離感 | |
| 35.「不思議」,科学の目の芽生え | |
| 自主性・主体性・意欲 | |
| 51.「基地」空間 | |
| 52.アフォーダンスの演出 | |
| 53.遊びの可視化 | |
| 54.遊びの保存 | |
| 55.片付けのための工夫 | |
| 56.遊びの場の保障 | |
| 57.集中して遊べる空間 | |
| 58.プレパレーション | |
| 自立と自律 | |
| 23.時間の可視化 | |
| 24.日課の可視化 | |
| 25.音で場面や行為を知る | |
| 26.流れをデザインする | |
| 27.「自分で」を支える | |
| 28.着脱の自立への配慮 | |
| 29.排泄の自立への配慮 | |
| 30.身近な手洗い場 | |
| 喜んで話したり 聞いたりする態度 |
|
| 39.ショウ&テルの機会 | |
| 40.仲間の共有 | |
| 41.保育単位の連携と柔軟性 | |
| 42.交流の拡がりを誘う空間 | |
| 43.育ち合いの仕組み | |
| 人に対する愛情と信頼感 | |
| 43.育ち合いの仕組み | |
| 47.命の祝福 | |
| 48.自己の成長の確認 | |
| 49.生活の振り返りの機会 | |
| 50.作品の展示 | |
| 他者を大切にする心 協調性 |
|